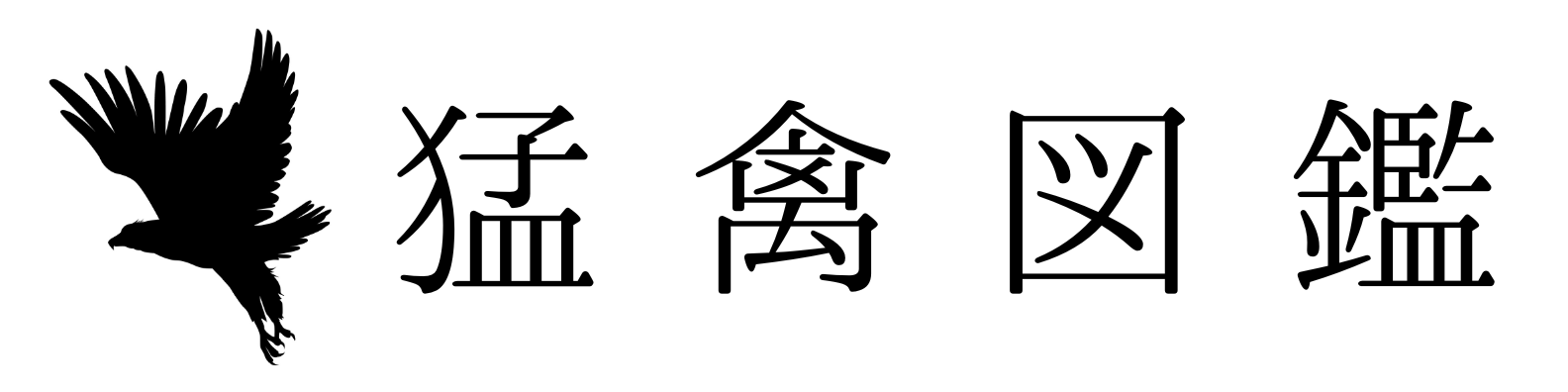鳥の中でも特に人気な猛禽類。実は種類によっては飼育できると知って「いつか一緒に暮らしてみたい」と夢見る方もいるかもしれません。しかし、猛禽類は私たちの暮らしに身近な犬や猫とは異なり、その飼育には特別な知識と覚悟、そして何より法律で定められたルールを守る必要があります。
この記事では、猛禽類の飼育を考える上で、絶対に知っておかなければならない2つの重要な法律と、特に厳しく規制されている「特定動物」という概念について、実際の条文も交えながら、分かりやすく解説していきます。
動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)
この法律は、家庭で飼われるペットから、動物園の動物まで、あらゆる動物の愛護と、適切な管理について定めた法律です。この法律の中で、猛禽類の飼育希望者が必ず知っておかなければならないのが「特定動物」という制度です。
【最重要】「特定動物」とは?
特定動物とは、「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物」として、政令で定められた動物のことです。
猛禽類の中でも、特に大型で力が強い種が、この特定動物に指定されています。
・特定動物に指定されている主な猛禽類
イヌワシ、オオワシ、ハクトウワシ、オオタカ、クマタカなど
これらの特定動物を飼育するためには、動物の種類や飼養施設ごとに、都道府県知事又は政令指定都市の長の「許可」が必要です。
第二十六条
e-Gov法令検索 – 「動物の愛護及び管理に関する法律」
1 動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
許可を得るためには、逸走を防止するための非常に頑丈な飼養施設の設置や、マイクロチップによる個体識別措置など、極めて厳しい基準をクリアしなければなりません。そのため、一般的なペットとしての飼育は、事実上不可能に近いのが現状です。
特定動物についてのさらに詳しい情報は、環境省 – 「特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について」をご参照ください。
鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
この法律は、日本に生息する野生の鳥類と哺乳類(鳥獣)を保護・管理するための、最も基本的なルールです。
【原則】日本の野生の猛禽類は、捕獲も飼育も禁止
この法律で最も重要なポイントは、「日本に野生で生息している猛禽類を、許可なく捕まえたり、飼ったりすることは固く禁じられている」ということです。
例えば、怪我をしたオオタカのヒナを保護したとしても、それをそのままペットとして飼育することはできません。
第八条
鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
e-Gov法令検索 – 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。
このルールがあるため、日本でペットとして飼育・販売されている猛禽類のほとんどは、海外から正規に輸入された、外国産の種ということになります。
地域ごとの条例について
上記の国の法律に加え、各都道府県や市区町村が、独自に動物愛護に関する条例を定めている場合があります。 例えば、特定の動物の飼育について、追加の届出を義務付けていたり、より細かい飼養施設の基準を設けていたりすることがあります。
猛禽類の飼育を具体的に検討する際には、必ずお住まいの自治体の動物愛護管理センターや、保健所に問い合わせ、その地域独自のルールがないかを確認することが不可欠です。
まとめ:法を守る責任
猛禽類と暮らすことは、大きな魅力と喜びに満ちていますが、同時に、その命を預かる重い責任と、社会の安全を守るための法律を遵守する義務が伴います。
この記事で解説した「動物愛護管理法」と「鳥獣保護管理法」、そして「特定動物」という概念を正しく理解することが、その夢への、責任ある第一歩となります。
憧れだけで判断せず、まずは正しい知識を身につけることから始めていきましょう。