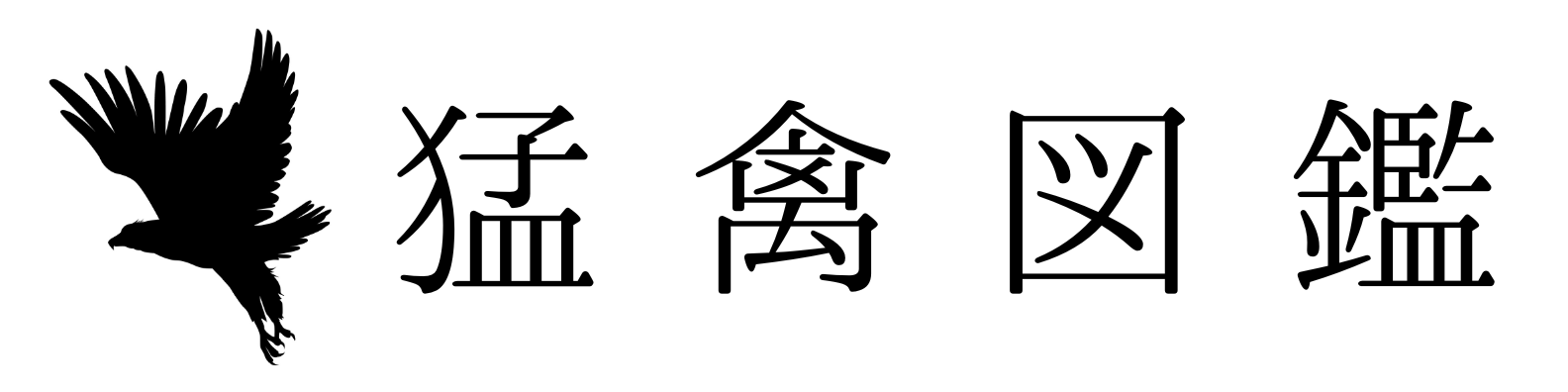「猛禽類」といわれて、正確にその定義を答えられますか?タカとワシって何が違うかわかりますか?
猛禽類が好きです!って言った時に、周りから「猛禽類って何?タカとワシって何が違うの?」と聞かれて正確に答えられなかったら少し悔しいですよね。
意識して調べないと意外とわからないその定義や違いについて、この記事を読めばその知識を周りにドヤ顔で披露できるようになるはずですので、まずはご一読してみてください。
猛禽類とは
猛禽類とは、他の動物を捕らえて食べる肉食性の鳥たちの総称です。そして獲物を捕らえるために進化した、いくつかの共通した特徴を持っています。
特徴①:鋭い鉤爪
獲物をがっちりと掴むための、鋭く頑丈な爪です。さまざまな種類の鳥が獲物の大小は違えど、獲物を狩猟しますが、実は足を使って獲物を捕らえるのは猛禽類だけです。
狩猟時だけでなく獲物の運搬、巣を作る際の枝の運搬や止まり木への移動にもこの鉤爪が役立っています。

特徴②:鉤型の曲がった嘴(くちばし)
猛禽類はすべて、先端が鋭く湾曲した嘴(くちばし)を持っています。湾曲しているのは、獲物の肉を引き裂くのに最適な形だからだと言われています。
また、嘴の形は食性によって猛禽類の間でも多少異なることが知られており、主に昆虫などを主食とする小型の猛禽類(チョウゲンボウなど)は小さく短い嘴であるのに対し、大型の獲物を捕らえる猛禽類(ハクトウワシ、オオワシなど)は大きく力強い嘴を持っています。

特徴③:優れた視力
猛禽類の視力は、人間の約2~8倍ほど優れていると考えられています。ある研究では、一部の猛禽類が中型の獲物を少なくとも約1.6km離れたところから見つけることができることが実証されており、はるか上空から獲物を狩猟する時に役立っています。

猛禽類の分類
猛禽類は「タカ目」「フクロウ目」「ハヤブサ目」の3つのグループに分類されます。
タカ目
タカ目は猛禽類の中で最も多くの種類が含まれる、最も一般的なイメージに合致する猛禽類です。タカ目ですが、ワシも生物学的にはタカ目の分類になります。そのためタカとワシの生物学的な違いはなく、厳密ではないもの主に大きさの違いで分類されている傾向にあります。
タカの仲間
タカ目の中でも小型~中型の猛禽類を指すことが多いです。ワシと比べてサイズが小さい分、狩りにおいては待ち伏せしたりチームで狩りをしたり、多様な狩猟方法を持っています。
ワシの仲間
タカ目の中でも比較的大柄な種族が多いのがワシです。体が大きい分、捕らえる獲物も大きくなりますが、パワープレイで狩猟することが多いです。
フクロウ目
フクロウ自体を知らない方はあまりいないと思いますが、フクロウが猛禽類だと知らない方はもしかしたらいたのではないでしょうか。
猛禽類の中でもまた違った特徴を持ち、正面を向いた大きな目、音を集めるお皿のような顔(顔盤)、そして音を立てずに飛ぶための特殊な翼と、夜の狩りに適応しています。
ハヤブサ目
タカ目とは少し離れたグループで、細く尖った翼を持ち、直線的な高速飛行を得意とします。
フォルムはタカやワシと似ていますが、サイズはタカよりさらに一回り小型な種族が多いです。ただその分ハヤブサはスピードに特化しており、急降下時のスピードは全動物の中でも最速と言われています。
まとめ
これで猛禽類とは何か、それぞれの種族の違いがわかったのではないでしょうか。
このサイトでは、今回取り上げた4つの種族の特徴や生態をご紹介しているので、気になる鳥がいたらぜひ見ていっていただけると嬉しいです。