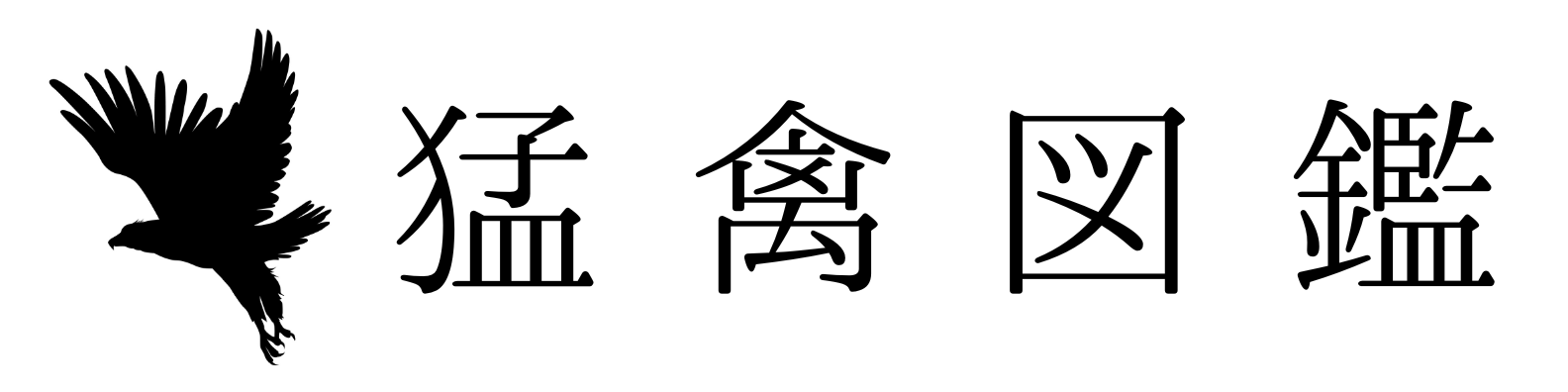ハチクマ
英名:Oriental Honey-buzzard
学名:Pernis ptilorhynchus
分類:タカ目タカ科ハチクマ属
和名は同じ猛禽類のクマタカに姿が似ていて、蜂を主食とすることに由来していると言われている。種小名の ptilorhynchus はギリシャ語で「羽毛のある(ptilo)嘴(rhynchus)」を意味しますが、これは嘴の付け根が羽毛で覆われていることに由来します。
ハチクマの特徴
どれくらいの大きさ?体の特徴は?
体長57-60cm、翼開長150-170cm。
羽の色や模様の個体変異が非常に大きいことで知られています。暗い褐色の個体から、白っぽい個体まで様々です。顔にはハチの攻撃から身を守るための鱗状の羽毛があります。飛んでいる時は、翼を浅いV字に保ち、頭部が小さく見えるのが特徴です。
どこに生息している?
シベリア南部から東アジア、東南アジアにかけて広く分布します。日本で繁殖した個体群は、秋になると東南アジア(フィリピン、インドネシアなど)へ渡り、越冬します。
平地から山地の森林に生息し、特に広葉樹林を好みます。
何を食べて生きているの?狩りの方法は?
主にクロスズメバチやアシナガバチなど、社会性のハチ類の巣を襲い、その幼虫や蛹を食べます。
ハチの巣を専門に探すハンターです。ハチの飛行ルートを追跡したり、地面を歩き回って地中にある巣を探し当てたりします。巣を見つけると、強力な足で掘り起こして破壊します。
絶滅は危惧されている?
IUCNレッドリストでは LC (低懸念) に分類されています。
日本では、生息地となる里山林の管理放棄や、針葉樹の植林による環境の変化が、餌となるハチ類の減少を通じて、個体数に影響を与えている可能性が指摘されています。また、渡りのルート上での密猟も脅威となります。
IUCNレッドリストとは、国際自然保護連合(IUCN)が作成している、世界で最も包括的な絶滅のおそれのある野生生物のリストです。正式名称は「The IUCN Red List of Threatened Species™」といいます。
IUCNレッドリストの分類
| 分類(英名) | 分類(和名) | 説明 |
|---|---|---|
| EX (Extinct) | 絶滅 | 最後の1個体が死亡したことが疑う余地のない種 |
| EW (Extinct in the Wild) | 野生絶滅 | 本来の生息地では絶滅し、飼育下・栽培下でのみ生存している種 |
| CR (Critically Endangered) | 深刻な危機 | ごく近い将来、野生での絶滅の危険性が極めて高い種 |
| EN (Endangered) | 危機 | CRほどではないが、近い将来、野生での絶滅の危険性が高い種 |
| VU (Vulnerable) | 危急 | 野生での絶滅の危険性が増大している種 |
| NT (Near Threatened) | 準絶滅危惧 | 現時点では絶滅危惧ではないが、将来的に移行する可能性がある種 |
| LC (Least Concern) | 低懸念 | 絶滅リスクが低く、保全上の懸念が少ない種 |
| DD (Data Deficient) | 情報不足 | 評価するための情報が不足している種 |
| NE (Not Evaluated) | 未評価 | まだ評価が行われていない種 |