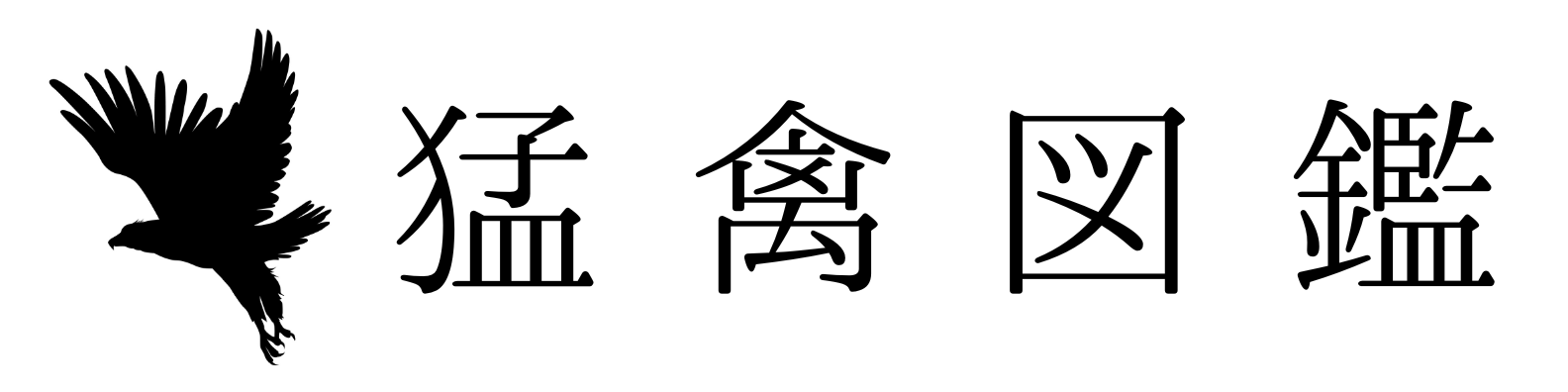ミサゴ
英名:Osprey
学名:Pandion haliaetus
分類:タカ目ミサゴ科ミサゴ属
魚食に高度に特殊化した猛禽類で、多くのタカ科の鳥とは異なる特徴を持つため、本種のみで独立した「ミサゴ科(Pandionidae)」に分類されます。魚を好んで食べることから別名Fish hawk(うおたか)とも呼ばれています。
ミサゴの特徴
どれくらいの大きさ?体の特徴は?
体長52-60cm、翼開長152-167cm。
背中側は濃い褐色で、頭部と腹部は白色です。目の周りには、嘴の付け根から首の後ろにかけて続く黒褐色の帯模様があります。翼は長く、飛んでいる時には手首の部分(翼角)がM字型に曲がって見えるのが特徴です。
どこに生息している?
安全な営巣地と魚類が豊富な浅瀬があれば、ほぼどこにでも生息できるため、南極大陸を除く、ほぼ全世界の大陸に分布します。非常に広範囲に生息する鳥類の一種です。
海岸、河川、湖、池、貯水池など、魚類が豊富に生息するあらゆる水辺環境に見られます。営巣場所として、水辺近くの樹木や、断崖、電柱、そして人工の巣台などを利用します。
何を食べて生きているの?狩りの方法は?
食事の99%以上を魚類が占める、完全な魚食性です。
水面の10~40メートルほど上空を飛翔またはホバリングしながら獲物を探します。獲物を見つけると水面に向かって急降下し、脚を前方に振りながら水面にダイブして魚を捕らえ、強力な羽ばたきで自分の体を水面から引き上げます。その後は空中で体勢を整え、止まり木まで魚を運んで食事をとります。
絶滅は危惧されている?
IUCNレッドリストでは LC (低懸念) に分類されています。
かつてはハクトウワシなどと同様に、農薬DDTの生物濃縮によって卵の殻が薄くなり、世界的に個体数が激減しました。しかし、DDTの使用禁止後、その個体数は目覚ましく回復しました。人間が設置した人工巣台を積極的に利用するため、保護活動が比較的成功しやすい種でもあります。日本では、海岸や大きな河川で一年を通して見られます。
IUCNレッドリストとは、国際自然保護連合(IUCN)が作成している、世界で最も包括的な絶滅のおそれのある野生生物のリストです。正式名称は「The IUCN Red List of Threatened Species™」といいます。
IUCNレッドリストの分類
| 分類(英名) | 分類(和名) | 説明 |
|---|---|---|
| EX (Extinct) | 絶滅 | 最後の1個体が死亡したことが疑う余地のない種 |
| EW (Extinct in the Wild) | 野生絶滅 | 本来の生息地では絶滅し、飼育下・栽培下でのみ生存している種 |
| CR (Critically Endangered) | 深刻な危機 | ごく近い将来、野生での絶滅の危険性が極めて高い種 |
| EN (Endangered) | 危機 | CRほどではないが、近い将来、野生での絶滅の危険性が高い種 |
| VU (Vulnerable) | 危急 | 野生での絶滅の危険性が増大している種 |
| NT (Near Threatened) | 準絶滅危惧 | 現時点では絶滅危惧ではないが、将来的に移行する可能性がある種 |
| LC (Least Concern) | 低懸念 | 絶滅リスクが低く、保全上の懸念が少ない種 |
| DD (Data Deficient) | 情報不足 | 評価するための情報が不足している種 |
| NE (Not Evaluated) | 未評価 | まだ評価が行われていない種 |
出典
- Chesapeake Bay Program – “Osprey”
- eBird – “Osprey”
- Audubon Guide to North American Birds – “Osprey”
- Animal Diversity Web – “Pandion haliaetus”
- IUCN Red List – “Pandion haliaetus”